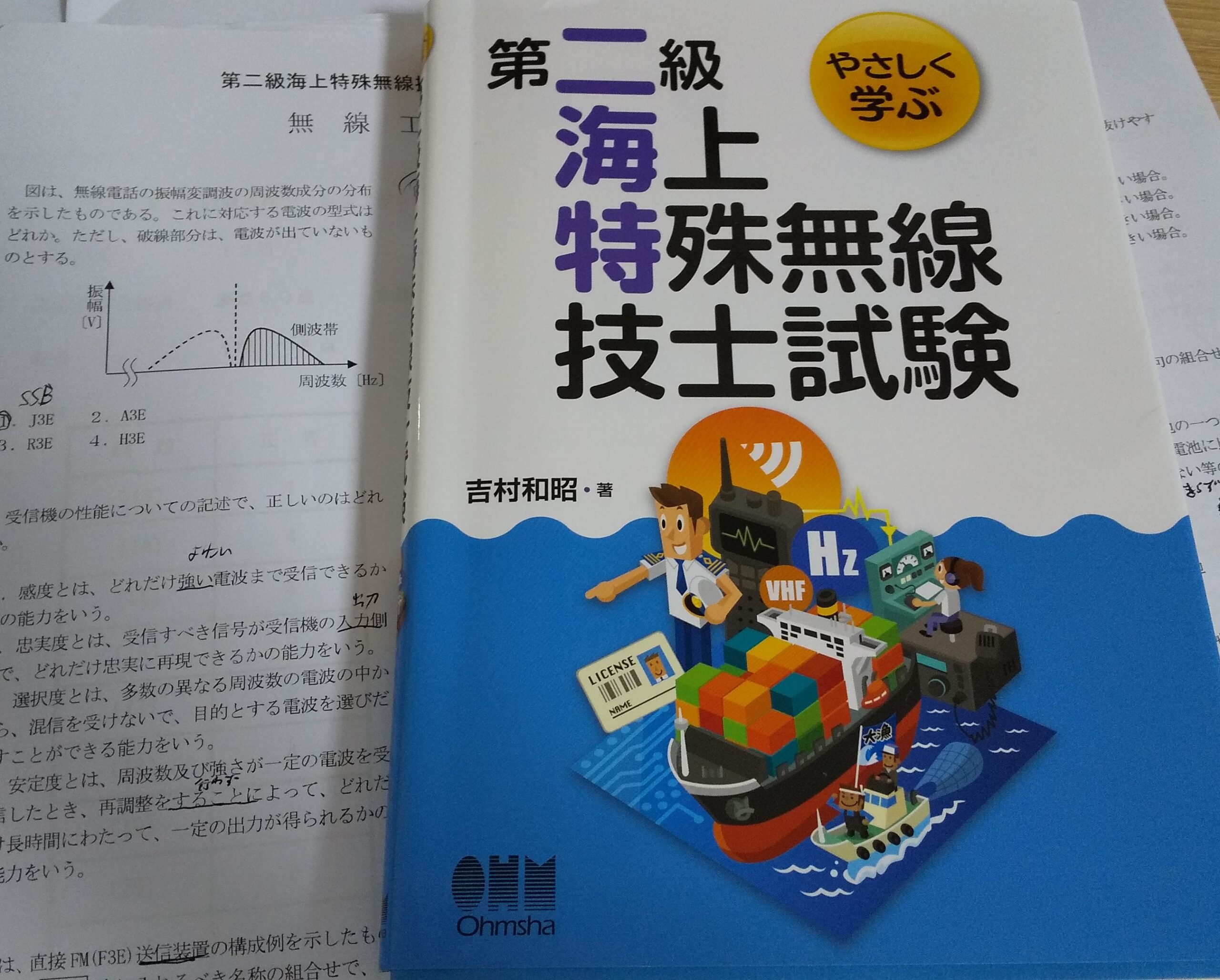①キャリアコンサルタントになろうとお考えの人、キャリアコンサルタント養成校ですでに勉強されている人に向けて、私の受験体験と、やってきた勉強方法を書いております。
さて、前回のブログで、前述しましたように、キャリアコンサルタントの養成校の授業は、キャリアコンサルタント試験向けの対策に特化した時間は、ほぼないです。
なぜなら、受験資格を得るために開催されているものであって、国家資格の試験に受からせるものではないからです。
さらに、週一回で、3カ月の授業です。これで、カウンセリングのプロを仕上げるには、そもそも無理があると思います。
授業の一環として、筆記も実技も、ちょっとだけ試験対策風なものがあるにはありますが、試験に準じていない「ミニ方式」のものだったので、それでは全然、万全とは言い難いのです。
まぁ、筆記試験は、講義に並行して、自分で勉強することができます。
しかし、実技の対策は、なかなかできないのです。
その前に、講習を受けている早い段階で、自分の性格・性状を理解してその性格・性状のままだと、キャリアコンサルタントの実技が受からないと気付くことが重要ですw
なぜなら、ほとんどの人は、話を聴くよりも話したい訳ですし、できれば自己の主張を相手に理解させたいとなる脳みその構造だからです。

中年・年配の人、とりわけ男性陣がどれだけ自分の今まで培ってきた説明口調を「お口にチャック」できるか、なのですw
私も、常々、説明口調になりますし、それも前置が長いのです。
それが出てしまう自分に、自分自身で気づくことは、絶対早い方がいいですね。
キャリアコンサルタントの実技試験は、説教オジサン・世話好きオバサンが、受かる面接試験ではないのですから。
今回は、そういった私自身にもあった性格傾向への不安を解消するために、ネットでいろいろ検索して、自分でできる面接・面談の基礎固めのために、購入した本を載せていきたいと思います。
マイクロカウンセリング技法|福原眞知子監修|風間書房
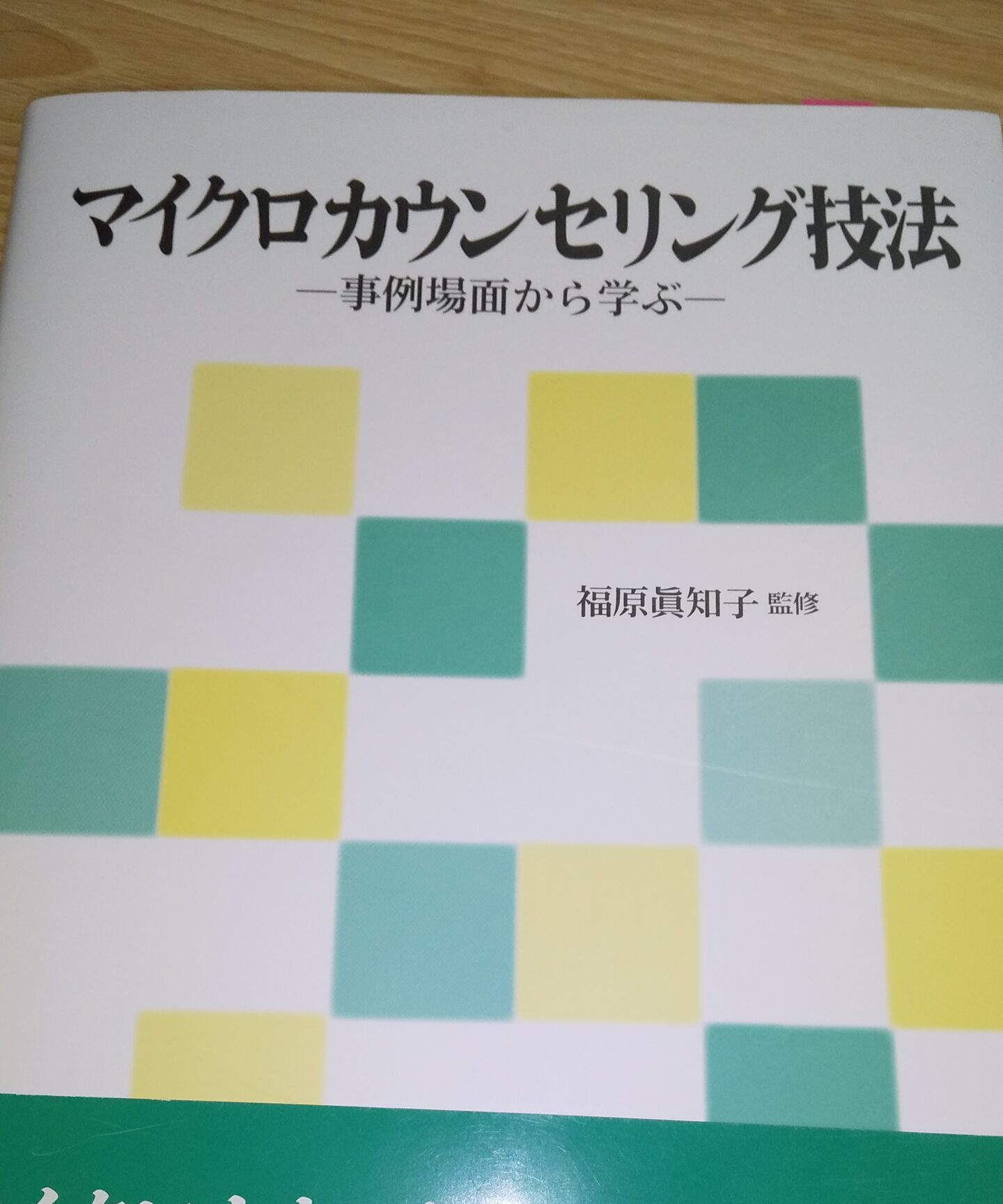
キャリアコンサルタントの講習の初めの方は、さらっと流しで学科に関することが授業でありますが、それが終わるとずっとロールプレイの講習になっていきます。
そのはじめのときは、まだよくわからないまま「素」の自分の人が多いのだと思いますが、早めに、どういったものがキャリア面談というものなのかを、知っておくほうが絶対に良いです。
このマイクロカウンセリング技法は、アメリカのアイビィ博士が編み出して、日本にはこの本を監修された福原先生が導入されたようです。いわゆる本家ですね。
養成校のテキストにも、後ろの方にw、このアイビィの「三角形」が載っていると思います。
「かかわり行動」から始まって、「開かれた質問・閉ざされた質問」、「はげまし・言いかえ・要約」、「感情の反映」。ここまでが基本的傾聴の連鎖としています。
キャリアコンサルタントの実技試験は15分です。短時間です。なので、ほぼここまでになると思います。
指示や説明は、試験では出すことがないと考えた方が無難なのかもしれません。(まぁ流れによっては「積極技法」まで行くのかもしれませんが、傾聴が不十分だと判断されて、危険かもしれませんね)
この本は、良い例・悪い例として、DVDが付いてきます。
というか、購入者のほとんどがこのDVD目当てなのだろうと思います。
DVDでは、ちょっと、極端な「悪い例」ですが、なんども見返して、面談時にやってはいけないというのを、目と耳で脳に叩き込むのがよいと思います。
養成校の講習でも、これを先に見るのと見ないのとでは、勉強の質に大きな違いがあるとおもいました。
プロカウンセラーの聞く技術|東山紘久|創元社
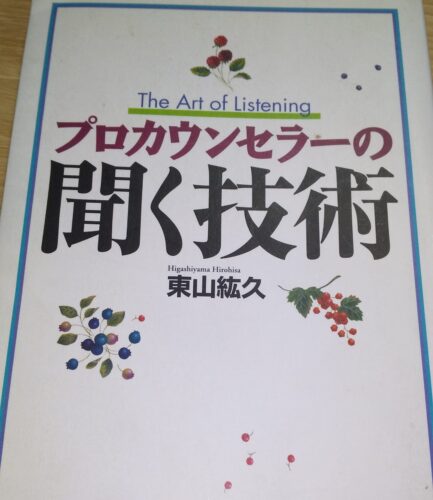
この本は、臨床心理士で京都大学の先生が書かれています。
私は、講習の初期にこの本を買いました。私の中の解説者や評論家を抑え込むためですw
「聞き上手」になることがカウンセラーやコンサルタントには必須の要件ですが、「素」のままで「聞き上手」な人は、そんなに多くおられません。
井戸端会議やネット上では、「ねぇ、ちょっと聞いて~」から始まり、個々が言いたいことを言うというのが普通です。最近は「待って!」と出だしに言うらしいですねw
この本はコラム風に構成されていて、
「1.聞き上手は話さない」
「9.他人のことはできない」
「14.教えるより教えてもらう態度で」
「20.評論家にはならない」
「25.説明しない」
「29.聞き出そうとしない」
などなど、普段オジサン・オバサンがやってしまうことを修正するための考え方が書かれています。
キャリアコンサルタントの資格を取っても、これらのことを面談時やってしまうキャリアコンサルタントもたくさんいます。養成校の講師にも、自己主張することが好きな人がいて、閉口しましたw
キャリアコンサルタント養成界隈または教育領域メインの人は、どうも指示的な人が多い印象です。相手が教えを受ける立場だからなんでしょうけど、これでは日本のカウンセリング界の立場は低いままなんでしょうね。
話を戻しますと、初期の段階でこの本に出会い、実技の試験の前に再度読んで、自分の起動修正が出来たことは、とても良かったと思います。
キャリアコンサルタントのためのカウンセリング入門|杉原保史|北大路書房
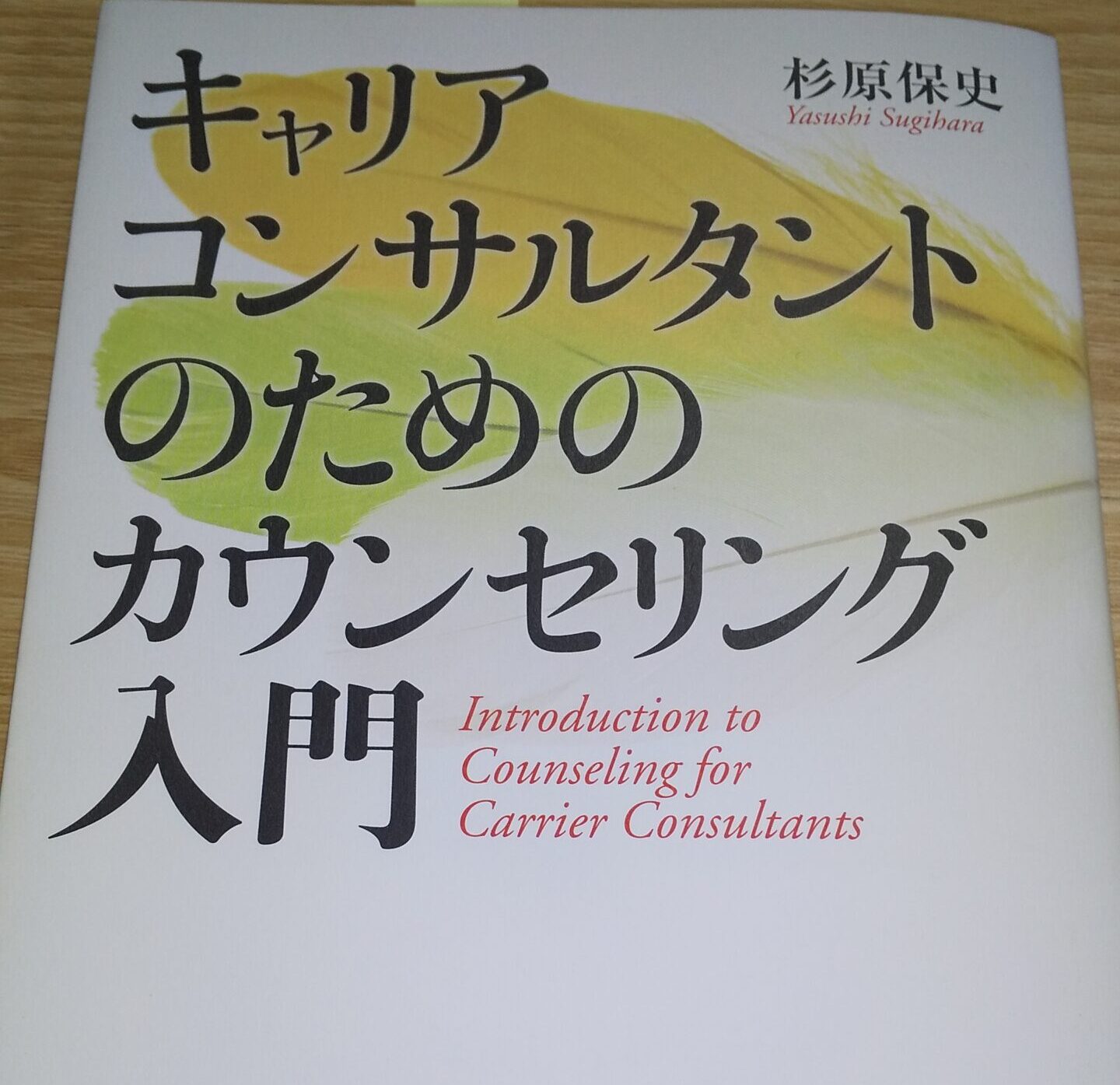
こちらも京都大学の先生が書かれている本になります。
題名が直球ですね!
この本は二部構成になっていまして、「実際編」と「理論編」に分かれています。
「実際編」は、心理カウンセラーとして、著者の体験したエピソードを交えながら平易に書いておられます。ここに書かれたことは、養成校では触れられません。時間が足りないこともありますが、心理学を学んだ人が教えている訳ではないからだと思います。
なので、養成校のロールプレイは、養成校のモノであって、実際のものとは違うという判断をさせてくれる良書です。
これがわかると、講習の中での「モヤモヤ感」もだいぶ解消されます。さらに言えば、キャリアコンサルタントの実技試験も、実際の面談とは違います。評価する人とされる人がいて、試験に合わせた線引きがあるからです。
皆さんがなぜキャリアコンサルタントになりたいのかを再度考えさせてくれる内容になっています。それぞれの立場や思いがあって、この資格を目指されているのだろうと思いますが、資格を取った先のことがわかります。
実技試験を受ける心構えも、先を見据えているのといないのとでは違ってくると思います。
答えはないので、読んでも「う~ん」と唸り「なるほどぉ~」となるのですけど、これが結構重要な時間なのかもしれないな、と思います。
後半の「理論編」は、学科試験に直結している内容です。
テキストや問題集は解説しているだけなのですが、それをもう少し踏み込んだところまで書かれていますので、記憶に残りやすいかな、と思います。
この「理論編」の初めの章における著者の文を引用しますと、
現在刊行されている多くのキャリアカウンセリングのテキストには、心理カウンセリングの代表的な理論が概説されているものの、その記載は非常に抽象的で大雑把のものが多いように思われる。このような状況では、キャリアカウンセラーの方のカウンセリング能力が上がらないのも無理はありません。
やさしく丁寧に、メインどころの理論家の理論を解説されていますので、きっと将来の力になるような気がします。
まとめ|キャリアコンサルタント試験の前にテキスト以外で読んだ本
以上の3冊が、私がキャリアコンサルタント試験の前に目を通しておいた本になります。
確かに試験の対策ではありますが、それ以前の個人の資質の矯正といってもいいかもしれない読書でした。
中年期になると、どうしても、口が先行して話が止まらない人が多くなってきます。
それをどのように調整して、話し手に寄り添いながら、自己一致するのかが、人の話を聴く仕事の第一歩なのだろうと思います。
因みに、この、木村周先生の本も、よくキャリコンの受験には必携と言われている本ですね。少々お高いのですが、この本からキャリアコンサルタント試験の筆記の問題が抜き出されて、出題されているというのがもっぱらの話ですし。もちろん、私も購入済みです。
②キャリアコンサルタントの試験を受験された人は実感されておられると思いますが、キャリアコンサルタント試験の筆記試験は、他の国家資格試験と比べても、難しいことはないと思います。
問題自体も素直な問題ですし、やればやるほど得点できる科目が多いので、早めに、覚えておくと点数はどんどん取れます。
試験の困難性を感じるのは、論述と面談の「実技」になってくる人が多いと思われます。
キャリアコンサルタント試験の「実技」は練習あるのみ!の意見もありますが、その練習にも注意点があります。
それは、養成校の生徒さん、同レベルの人だけで、ロールプレイしてもあまりカウンセリングの力が付かない。むしろ、素人同士で評価し合うことが悪影響になることも考えられます(過度に褒め合うとか、意見が対立するとか、ボス的な人物が言い負かす、それに皆が同調する、など)。
それでやる気をなくす人もいます。
そんな風になるのだったら、プロや先駆者の教え、良書を読んで、面談の基本的な考え方や理論を、うっすらでも早めに感じ取っておくことの方がずいぶんマシです。
試験勉強だけの話ではないですが、基本がまだ出来ていない人が、受験に対する不安からなんとなく集まっても、あまり良いことにはならないです。

スポーツでもそうですが、必ずいい指導者を付けなければ、その人の今まで生きてきたやり方のクセから抜けられないのです。
そうなる前に、先駆者の良書に触れて、自分のクセを本によって諭されて感じる方が、実技の力になる気がします。
以下は養成校のテキスト以外に私が購入した本の第2弾になります。
キャリアカウンセリング|宮城まり子|駿河台出版社
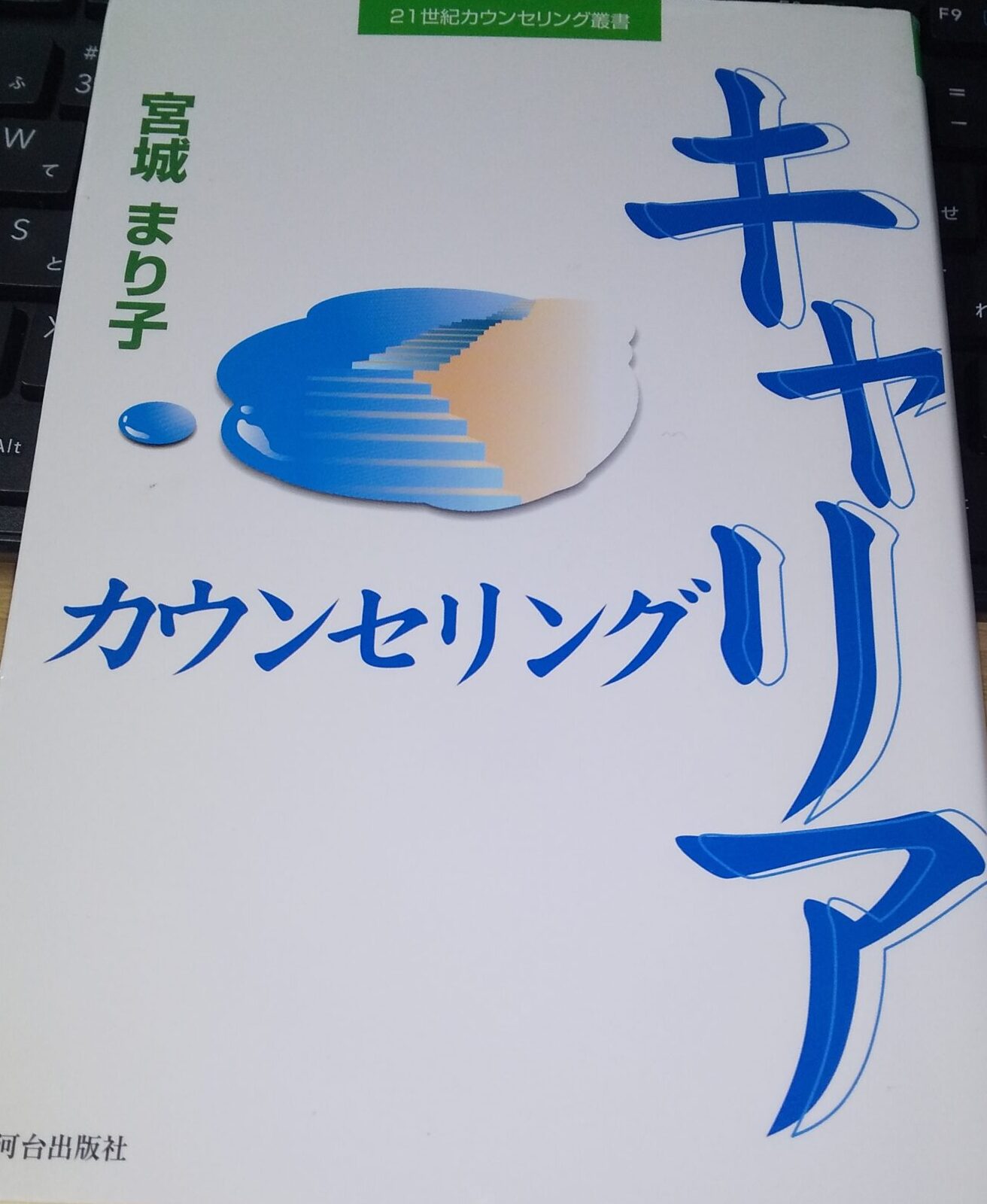
ねむの木学園の宮城まり子さんではなく、大学の先生で臨床心理士でいらっしゃる宮城まり子さんです。
キャリアに関する心理学ではとても有名な先生のようですね。
この本の第3章「キャリアカウンセリングの方法」。第4章「キャリアカウンセリングの進め方」、そして「キャリアカウンセリングの効果的な面接方法」は、実技試験に臨む前に、おさえておくべき基本的なことを分かり易く書いておられます。基本的といいましても、やるのは本当に難しいのですけど。まぁ、簡単であると永遠に思えないのが、もしかしたらカウンセリングの正解なのかもしれませんね。
前半には、理論のことも書かれていますので、筆記試験のために、理解を深めておくこともできました。
キャリアの心理学|渡辺美枝子編著|ナカニシヤ出版
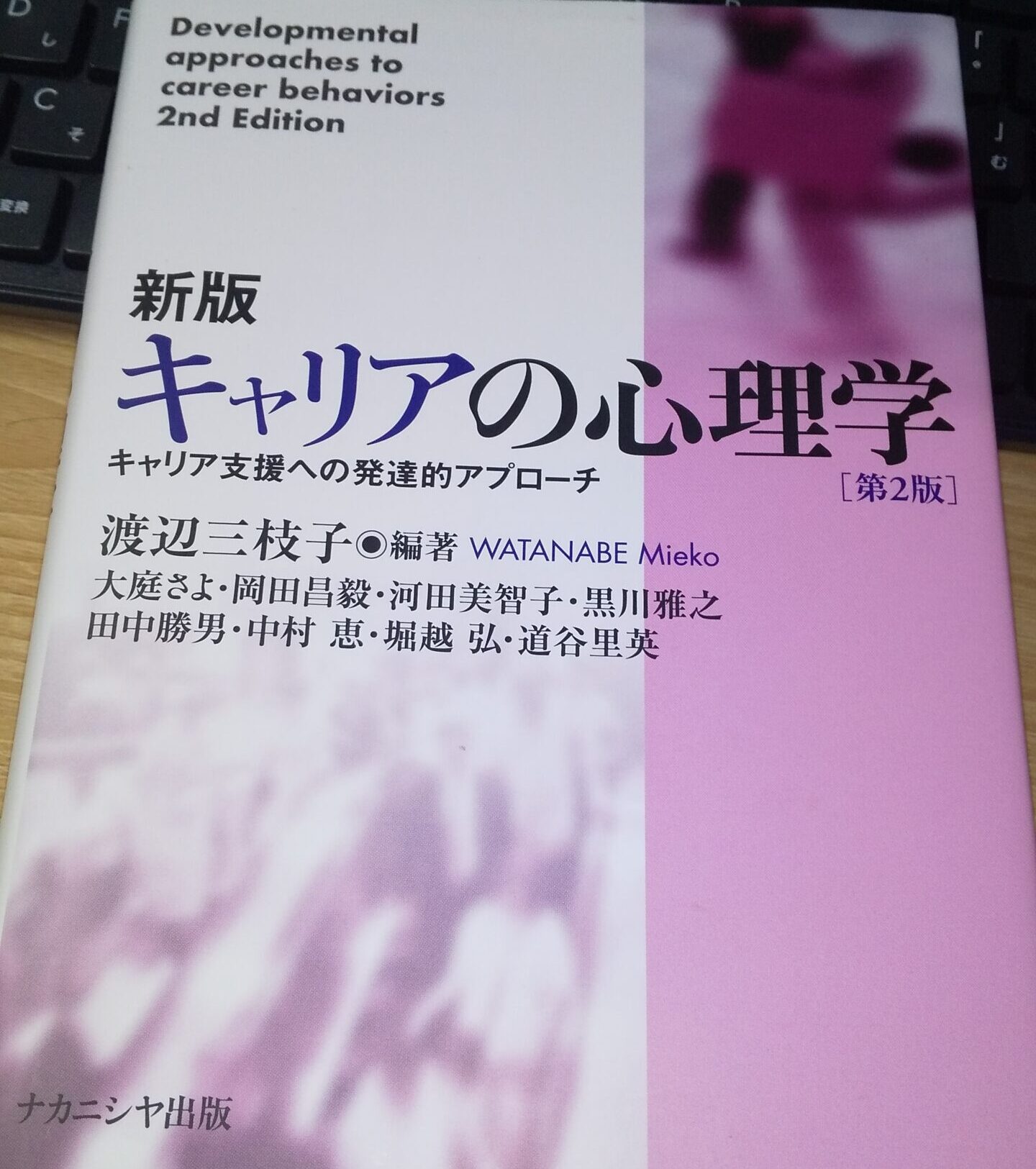
多くのキャリアコンサルタント受験対策のサイトやブログでお勧めされている本です。
押さえておきたいメイン理論家の解説書ですね。
スーパー、ホランド、サビカス、ジェラット、クランボルツ、シャイン、ホール、シュロスバーグ、ハンセン
表や図解もあるので、分かり易いですが、キャリアコンサルタントの試験対策としては少し掘り下げすぎな部分もあるので、時間のない人は、どこかで見聞きしたもの以外は、取捨選択されるのもいいと思います。
そして、試験に受かり、実地の前に、じっくり読んだらよいと思います。
それと、将来的に、キャリアコンサルティング技能士2級を受けるつもりの人は、持っておいてもいいかなと思います。
キャリアカウンセリング再考|渡辺美枝子編著|ナカニシヤ出版
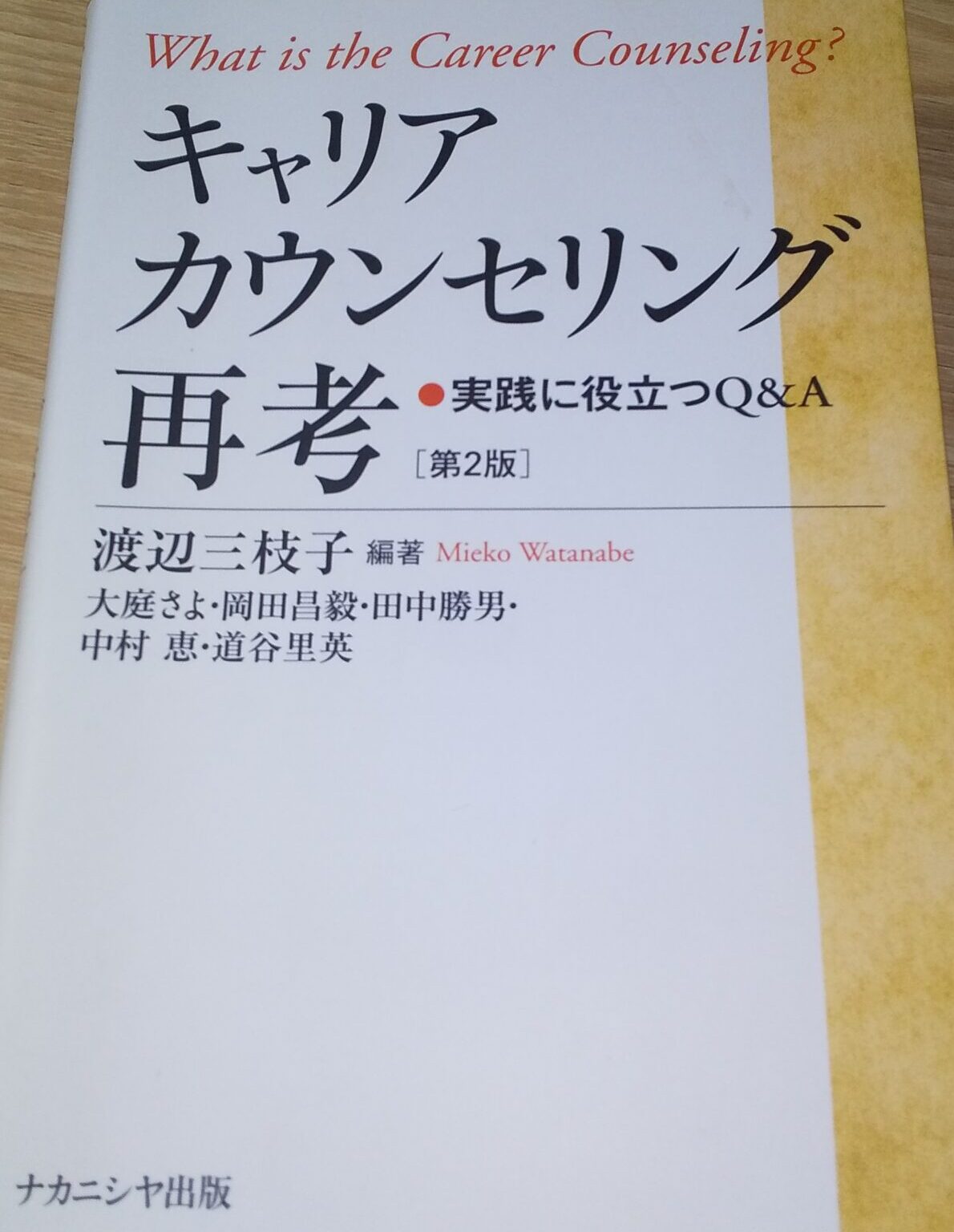
こちらの本は、キャリアに関する様々な疑問・質問に答える形式になっています。
全部で50の問いがあって、わかりやすく説明されています。
基礎的なものや、「そもそも論」的なことから、実践において気を付けるべき点などを書いています。
どうしてキャリアコンサルタント試験を受けるのか、どのようなキャリアコンサルタントになりたいのかを、キャリアコンサルタントになる前に、ご自分で、ご自分のキャリアを考えるためにも、とても良い本だと思います。
まとめ|キャリアコンサルタント試験の前に読んだ本
本を読むことと、実技の練習は、一見かけ離れていると思われるかもしれません。
でも、多くの受講者は、実技の練習を「素」の状態でやり過ぎると、お互いがまだ人の話を聴ける状態ではないので、主張の押し付け合いになったりします。
実は、養成校の講義の間でも、それは起こるのです。人間の承認欲求が、過去生きて来た考え方を表出させるのでしょうか。
そうなる前に、さらっとでも、この分野の大家の先生の書かれた本に目を通しておくと、講義の内容が全然違ったものに見えてくると思います。
キャリアカウンセリングは、相談者の話をただただ聴いているわけではなく、話を聴きながら、頭の中で、グルグルと思考作業をしているのです。その中には、「思ったことをすぐに言う」という日常の脳みその働きではなく、取捨選択しながら言葉を紡いでいくのだと思います。
因みに、以下の1冊は、少々お高いですが、キャリアコンサルタントの試験を受け、キャリアカウンセリングに携わるのなら、持っておいた方が良い本です。この本から、筆記試験が抜き出されて出題されているというもっぱらの話ですし。