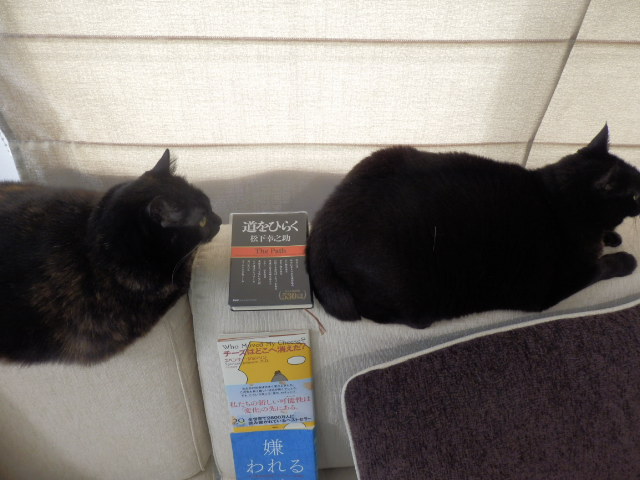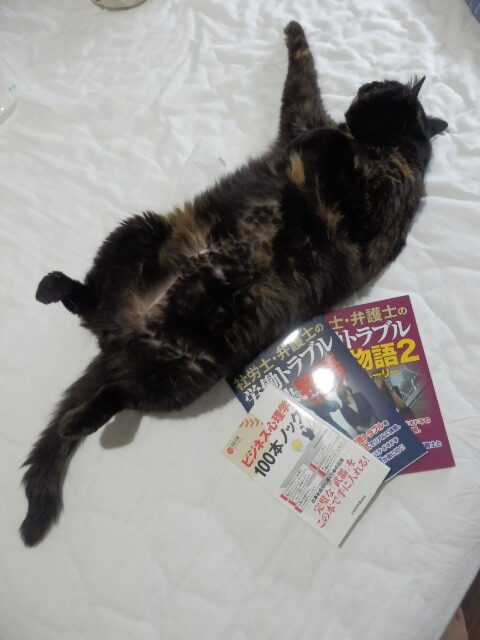今回は、自己啓発に関してのベストセラー3冊を、挙げてみたいと思います。
ベストセラー。
みんなが読んでいるものは、おそらく良いはず!という趣旨で購入しました。
そもそも、この種の本は、学習とか勉強といった意味合いのものではなく、商売人それ以前の、人間としての心の糧・生き方の指針になるものですので、折を見て何度も読み返すものだと思います。
人によっては、合う・合わないも出てくるかもしれませんが、合わないなら合わないなりに、得るものもきっとあることでしょう。
今、その内容が合わないだけで、将来的に考えを修正したときに、合致する内容かもしれませんし。
私は10代~20代の若いころには、「自己啓発」という言葉やその本に関心がありませんでした。若い時特有の驕りだったと思います。「そんなことをいちいち本で読まなくても大丈夫!」という。
しかし、年齢を重ねてきて、これからどう生きていくのかに関心が増してきたというのは、ずいぶん遠回りをしてしまっていますね。
まあ、でも、タイムマシーンがあって今の私が、若いころの私に「自己啓発本を読めよ!将来困るぞ!」と言っても、聞く耳を持っているのかは、はなはだ疑問ではありますw
道をひらく|松下幸之助著|PHP
ちなみに、サムネイルの写真では、猫と猫の間に、この本で道を開いています。
実はわたし、大阪の松下電器(パナソニック)の本社所在地のある市で生まれ育ちました。
地元の人は、松下電器がパナソニックに名称が変更してずいぶん経つ今でも、松下と言いますw
小さいころの友達のお父さんの多くは、松下の工場で働いていましたし、その友達自身も、同じように松下に勤めている者もいました。大学のクラブの先輩や同期だった者も、松下に入社しました。
松下になじみがあるのですが、松下翁の書籍を読むのは初めてになります。
ちなみに、松下本社の正門の横に「松下歴史館(現パナソニックミュージアム)」があるのは知っていたのですが、行ったことはありません。なぜかしら、申し訳ない気持ち。
(この記事を書いて、地元に行ったときの帰りに、松下記念館に寄ってきました!なんとゼロ円ですが、とてもいい博物館ですよ!)
東京都内の人の東京タワー、奈良市民の東大寺のような「いつでも行ける」感覚に似たものが、今まで行かなかった原因かもしれないです。
さて、こちらの本「道をひらく」は、1968年に初版されて、私の持っているもので、なななんと259刷!になっています。
つまり50数年読み続けられているすごいエッセー集です。
(因みに、ググって調べますと、増刷ランキングというのがありまして、松下翁の「道をひらく」は、なんと第2位だそうです!1位は「サラダ記念日」でした)
見開きで、一つの話ですので、読みやすいです。121編あるようです。
内容は、謙虚、三省(振り返って反省すること)という言葉がよく出てきまして、一人の日本人としての在り方を教えてくれています。
そうすることで、国家の安定と繁栄につながるとも。
ビジネスをしていると、儲けのための「考え」が暴走して、「自己さえよければ」と思ってしまったり、考えに固執したりすることがあります。
これらは、暴走すると「コンプライアンス」に引っかかっってくることもありますので、心のストッパーとして、この本はとても有用だと思います。
「今だけ、金だけ、自分だけ」という現代の風潮ではない心の部分を、
日本一の商売人の本から教わるのは、なんとも感慨深いものです。
チーズはどこへ消えた?|スペンサー・ジョンソン|扶桑社
こちらの本は、2000年に初版されて、104刷となっています。世界で読まれている名著の一つです。
(因みに、後で判ったことですが、増刷ランキングでは、5位になっているみたいです!)
本屋さんでよく見かけていたのですが、ようやく今になって購入した次第です。
薄い本ですので、小一時間もあれば読めました。
内容は、ネズミ2匹と小人2人が出てきて、まあ、ほとんど小人の物語なのですが、生きていく上で、変化にどう対応していくのか、そして、その時の心の持ちよう、などが書かれています。
今ある状況や考えに固執するという性質を人間はもともと持っているので、どうやって変化を受け入れていくのか、読みながら実に考えさせられます。
例えば「老害」という言葉があります。自分の経験値のみで、ものごとを判断して変化を好まない偏屈なおじいさんを想像しますが、実は20代30代の会社員にも、この性質は出てきます。
彼らは、今まで通りのやり方にこだわって、新しいことに反発します。
なぜなら、新しいことに馴染むまで、ある意味苦痛を伴うことを知っていて、なによりめんどくさいのです。
人が、人をマネジメントする仕事は、この「変化に反発する人間」をどうやって扱っていくのかということが、ひいては企業の存続にかかわってくる重要な事だろうなと思います。
このあたりのことは、ユーチューブで、キミアキ先生がどこかの話で話されていました(たくさんありますし、タイトルで内容が思い出せないのです、すみません)。
嫌われる勇気|岸見一郎・古賀史健|ダイヤモンド社
この本も本屋のランキングの棚で、よく見かけていたのですが、今になってようやく読みました。
(なんと、こちらは、続編の「幸せになる勇気」と合わせて、世界で1000万部を超えたようですw)
心理学者アドラーの考え方を、哲人と青年の対話文で教えてくれています。
対話文ですし、読み手にわかりやすいように、話は進んでいきます。
まあ、この青年の性格が、あまりにヒネクレているが気になるところでした。
議論好き、腑に落ちるまで時間がかかる、融通が利かないという演出なのだろうとは思いますけどね。
あと、タイトルの妙味といいますか、タイトル付けがセンセーショナルなので、それも発行部数の増大に影響したのだろうとも思いました。
阿諛追従や、承認欲求を捨てること、 まあ、日本の「同調圧力」が強い世の中で、凡人には難しいこともありますが、本当の自由はその先にあるということを教えてくれます。
まさしく、嫌われる勇気です。
人には、おせっかいなところが、誰しもあります。モラルハラスメントなんていうのも、強度なおせっかいであると言えるかもしれません。
「あなたのために言っている!」は、はたして、本当に100%そうなのか?ということですね。
で、この「嫌われる勇気」にあるように「それはあなたの課題、これはわたしの課題」と分けて考えることができれば、もうちょっと、日本の社会も、平穏な世の中になるのではないかなと思ったりもしました。
たとえば、親子関係、夫婦関係、友達関係、学校関係、地域住民関係、職場関係、などなど。
で、この本の話を突き詰めていくと、共同体感覚、他者貢献というワードになります。
これって、始めに紹介した松下翁の考え(謙虚、国家の安定・繁栄)と、通じるものがあるのかな、などと思ったりもしました。
まとめ|ビジネスを始める前に100冊読む②
SNSなどをみると、自らを浮揚させるためにだけに他人とつながり、自己利益追求だけにそのつながりを切っていく「キラキラさん」がおられます。
キラキラさんの中には、他者を助ける風に話し、絆や協力という優しい言葉を使っていますが、本当は他者を土台にしたいだけの人が、本当にたくさんいます。
でも、それは長く続かないものです。まぁ、いったん凋落したとしても、手を変え品を変え、また出てくるんでしょうけど。
これはもう、個人の生き方に関わってくるので、キラキラするのも、キラキラに惑わされて追従するのも、仕方のないことなのかなとも思います。
結局のところ、それはキラキラさんの課題であって、こちらの課題ではないのです。
他人がどうより、自分がどうあるのが正解なのかを考える方が、精神衛生上もいいですね。